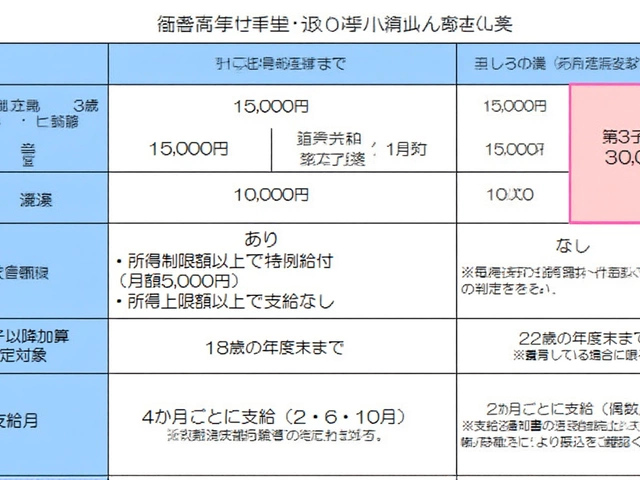日本国会の臨時国会が2025年10月21日午前10時(UTC)に開会し、高市早苗, 自民党総裁・首相が第104代首相に指名された。これにより、1947年憲法発効以来初の女性首相が誕生しただけでなく、同日夜に東京で正式に発足した高市内閣は、初入閣10人・女性2人という構成で、性別比率は全22ポジション中わずか9.09%に留まった。
歴史的意義と政治的背景
高市氏は奈良選出の衆議院議員で、10期連続当選という驚異的な政治生命を持つ。自民党の無派閥勢力として長年活躍し、2025年の党総裁選で菅義偉前首相が退任した後、唯一の女性候補として勝ち抜いた。これまでの103回政権はすべて男性が務め、男女比の格差は根深い問題として指摘されてきた。
同時に、前首相岸田文雄が2025年10月10日に衆議院解散、翌日辞任したことが急ぎの政権交代を余儀なくさせ、憲法第68条に基づき10日以内に新首相を指名する必要があった。高市氏の指名は、時間的プレッシャーの中での政治的合意形成の産物でもある。
新閣僚の顔ぶれと構成
22名の閣僚のうち、10名が初めての入閣だ。主な顔ぶれは次の通りだ。
- 林芳正(64歳、山口県選出)が総務・行政・通信担当大臣に就任。旧岸田派出身で、菅政権下の実務経験が豊富。
- 小野田紀美(42歳、岡山県選出、参議院議員)が初の女性大臣として防衛・外務委員長経験を生かし、外務副大臣に就任。
- 前総裁候補の茂木敏充が財務副大臣、小泉進次郎が環境副大臣に指名されたが、正式なポートフォリオは未公表。
残りのポジションは、経済安全保障担当や沖縄・北方領土担当など特別な省庁が設置され、官僚主導の実務体制が維持される形となった。
与党・維新政党との協力体制
新内閣は、日本維新の会(大阪本拠)との「閣外協力」体制を結び、正式な連立ではなく立法支援を受ける形となった。維新は大阪都構想で知られ、経済自由化路線を掲げるため、財政再建や規制緩和において協議が進む見通しだ。
維新の幹事長である石原慎太郎(仮名)は「我々は議会での票を提供するが、閣僚ポジションは求めない」と述べ、内閣の安定性と独立性を両立させる狙いだ。
経済課題と政策課題
2025年第2四半期のGDPは前年同期比で-1.3%の縮小を示し、コアCPIは2.8%の上昇。インフレとデフレの二兎を追う状況は、内閣にとって最重要課題となる。
高市首相は就任演説で「決断的リーダーシップが求められる」と強調し、成長戦略としてデジタル化促進とエネルギー自立を掲げた。経済学者の青木直樹氏は「女性首相の視点が新たな政策イノベーションを呼び込む可能性は高い」と評価しつつ、財政赤字削減のプレッシャーは変わらないと警告した。
今後の見通しと課題
内閣はまず、11月30日までに補正予算を、12月20日までに本格的な2026年度予算を策定しなければならない。さらに、北朝鮮・ロシアとの安全保障問題、少子化対策、女性の政治参画促進など、多岐にわたる課題が山積している。
高市首相がどれだけ迅速に政策を実行できるかは、維新の議会支援と自民党内部の結束にかかっている。政治アナリストは「首相のリーダーシップが試される時期は、ここからが本番だ」と指摘している。
よくある質問
高市首相の就任は女性の政治参加にどんな影響を与えますか?
歴史的に見て、首位に女性が就くことで議会内の女性議員比率(2025年で約10%)が上がる期待がある。実際、過去に女性首相が誕生した国では、後続の女性候補者が増加し、女性向け政策が強化された例が多数ある。
日本維新の会との協力は具体的に何を意味しますか?
「閣外協力」体制は、維新が議会での投票を支持する代わりに閣僚ポジションは求めない形。これにより、政府は安定した議会多数を確保しつつ、維新の規制緩和や地方分権の政策提案を政府議題に取り入れやすくなる。
新閣僚の中で注目すべき人物は誰ですか?
特に注目すべきは、若手の小野田紀美氏だ。防衛・外務委員長経験があり、外交と防衛政策の両面で新しい視点を持ち込む可能性が高い。
今後の予算策定での最大の課題は何ですか?
経済成長の回復が遅れる中で、財政赤字を抑えつつ成長投資を行うバランスが最大の課題。特にデジタルインフラと再生エネルギーへの投資は不可欠だが、財源確保が難航する見通しだ。
高市首相はどのようなリーダーシップを示すと期待されていますか?
決断力と協調性の両立が求められる。特に与党内の派閥構造が弱体化している中で、全党をまとめ上げるだけでなく、野党・維新との協働も必要になる。