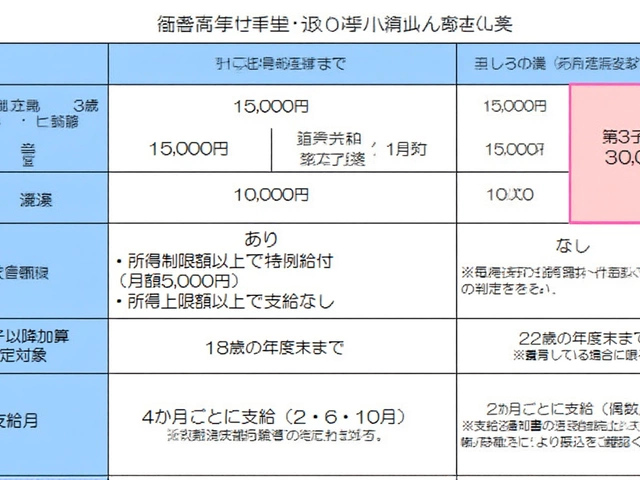明日ブルペン、焦点はフォームの同期と球速の回復
球団は慌てていない。本人も落ち着いている。右上腕の張りで負傷者リスト入りしていた35歳の前田健太が、復帰への階段を一段ずつ上がっている。本人いわく「順調」。次の関門は明日のブルペンだ。テーマははっきりしている――投球フォームの“ズレ”を直し、球速とキレを取り戻すこと。
前田は遠征先で約40分のリハビリ中心メニューを消化。可動域、肩周りの筋出力、下半身との連動を確認したうえで、直近のブルペンでは35球を投げた。感触は良好で、球団スタッフとも細かく映像をチェック。フォームのタイミングを合わせることで「メカニクスの調整で球速を上げたい」と狙いを口にする。単なる再発防止ではなく、パフォーマンスの最適化まで視野に入れているのが今の段階だ。
彼が言う“ズレ”は、小さく見えて積み重なると大きい。着地のタイミングが早ければ体重移動が前へ流れ、リリースが遅れやすい。逆に上半身が先に開けばボールは抜け、コマンドを損なう。結果、球速が落ち、回転効率も下がる。上腕への負担が増えるのもこの局面だ。前田の修正ポイントは、下半身の始動と肩・肘のしなりを同じリズムに戻すこと。ここがハマれば、同じ力感でもボールは自然と走る。
今回のブルペンでは、直球のキャリー(打者手元での伸び)と、スライダーやスプリットの軌道管理を重点確認する見込み。MLBでは球団のトラッキング機器を使って回転数や回転軸、リリースの再現性を可視化するのが一般的だ。数値がそろい、翌日の張りが出なければ、強度を一段上げる。急がず、でも迷わない。そんなステップ設計になっている。
ブルペン前後の様子も落ち着いていた。試合前にはエンゼルスの大谷翔平と笑顔で言葉を交わし、練習後には大谷がブルペンで37球を投げ込み、ブレーキングボールの精度を入念にチェック。コロナ禍以降、日米をまたぐ選手の交流は限られがちだったが、こうしたやり取りはプレッシャーの中で戦う選手にとって良いガス抜きになる。
前田は復帰ロードを「健康+上積み」でデザインしている。つまり、痛みが引いたから投げる、では終わらない。リリースの高さ、体幹のブレ、フォロースルーまでを含めて“最も負担が少なく、最も威力が出る”形を作る。2020年以降の投球で磨いてきたスライダーとスプリットは、フォームの同期が決まるほど効果が増す。真っすぐとのトンネルが揃い、打者の反応が一瞬遅れるからだ。
- 痛みや張りの再発がないか(特に翌日の反応)
- 直球の回転効率とリリース位置の再現性
- 変化球のキレとゾーン内外の投げ分け
- 下半身主導の動きが最後まで維持できているか
上は前田が踏むべきチェック項目の基本形だ。これらが揃えば、次は生き打者相手のライブBP、もしくは実戦形式のリハビリ登板が見えてくる。球数は40〜60球、その次に70〜80球と段階を踏むのが通例。リカバリーの手応え次第で、先発ローテに合流するタイミングが決まる。
チーム事情を考えれば、彼の復帰は先発陣の安定に直結する。ベテランのゲームメイクは、序盤の無駄球を減らし、中継ぎの過負荷を防げる。球数を抑えながら3巡目をどう乗り切るか。前田が得意とするのは、打者の反応を見ながら配球を微調整し、同じ球速帯に見える球を重ねることだ。球威だけで押し切らず、組み立てで勝つ。
今回のケースで気になるのが球速だが、無理に数字を追いかける必要はない。大事なのは「遅く見せない球」。回転の質とリリースの遅れを減らすことで、表示より手元で伸びる。フォームの“同期”が整えば、真っすぐは生き、スプリットはより落ち、スライダーは曲がり始めが遅くなる。すべてが連動して効いてくる。
ロードマップはこうだ。明日のブルペンで強度と再現性を確認→翌日の状態をチェック→もう一度強度を上げたブルペン→ライブBP→マイナーでのリハビリ登板。ここまでクリアできれば、先発復帰の目安が立つ。球団も本人も、段階を飛ばすつもりはない。
ファンが見るべきサインは、投球後の情報に多い。本人コメントに「指にかかった」「抜け球が減った」といった言葉が戻るか。捕手のミットが動かず、投球の着弾点が揃っているか。それが整えば、復帰後の初戦からゲームを作れるはずだ。
次の一歩は“質の高い”35球の先へ
すでに消化した35球は通過点にすぎない。次は配球を想定しながら、強弱をつけた実戦的なブルペンへ。カウント不利からのスライダー、真っすぐでカウントを取り、スプリットで空振りを狙うパターンをどこまで再現できるか。フォームの同期が決まれば、指先の感覚が戻る。そこからが本当の「復帰準備完了」だ。
表情、言葉、練習の強度。どれを取っても、今の前田は前だけを見ている。焦らず、でも確実に。明日のブルペンが、復帰への現実的な一歩になる。